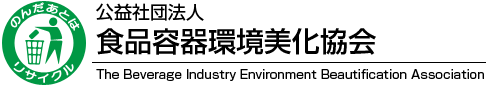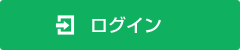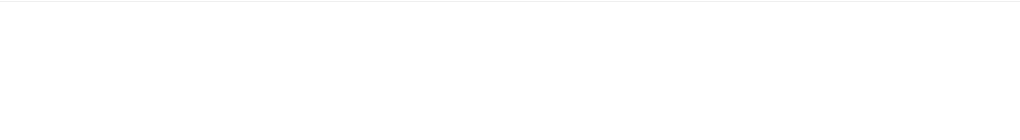
第25回(2024年度)環境美化教育優良校等表彰(審査委員長講評)

審査委員長
東京学芸大学名誉教授
小澤 紀美子 氏

審査員を代表して、講評を述べさせていただきます。今回、最優秀校に選ばれた学校においては、いずれも、地域のおかれた環境や地域の特性を踏まえ、先輩たちの活動を継承しながら、地域一体となった活動を行っており、学校の先生方もそうした地域の特性を意識されて、指導にあたっていることが十分伺われました。
今回の審査では、次の4つの評価の基準を設定しました。簡単に申し上げますと、①独創性があり、継続的・持続的な取り組みであること、②活動内容が客観的根拠を持って科学的・実践的な学びと結びついていること、③地域と連携していること、④活動が広がっていること、です。ただ単に容器をリデュース・リサイクルするという観点からだけではなく、探究というプロセスを通して「学び合い」と「学びの深まり・広がり」を実感しているとことが大事です。先ほどの最優秀校に輝いた4校の紹介映像を通して、そのことがご理解いただけると思います。
文部科学大臣賞を受賞した「鹿児島県肝付町立岸良学園」は、ウミガメ保護活動が保護だけにとどまらず、地域住民と連携しながら、科学的根拠に基づいた多彩な取り組みを進めている実践力と挑戦力に敬意を表したいと思います。さらに、ウミガメ科という独自の科目を設定し、「セレンディピティ」とも言うべき専門的な力を引き寄せる力を発揮して、水族館の方々との連携などにより、探究的な学びを深め広げていることは、改めて児童生徒さんは教科書だけで学びを深めているのではないということを教えていただきました。
農林水産大臣賞を受賞した「福井県福井市美山中学校」の皆さんには、甚大な被害をもたらした福井豪雨を乗り越えて復興に尽力してきた長年のご努力に敬意を表したいと思います。近年、世界各地で気候変動による災害が多発している状況下、地域住民と協働で環境保全に尽くす実践力や対応力は、日本各地のユースの取組みへの大きな刺激になることと考えます。さらに「みやま」という名前は、川端康成が「美しい日本」と表現したように、日本の地域を表す言葉とも言えます。「協働の力」による「美山しぐさ」という言葉が示すように、「たのもしさ・たくましさ・ゆかしさ」という日本のすばらしさを発信していただきたく、今後も期待しています。
環境大臣賞を受賞した「福島県只見町立只見中学校」では、新聞紙レジ袋を作製するという具体的な活動を通して、地域住民に影響を与えた素晴らしい取り組みです。特に日本の社会システムを考えていく時に、オルタナティブ(代替策)の発想をもちづらい日本の地域社会にあって「プラスチック製のレジ袋」に注目して実践を通して、地元のコメ農家さんへも影響を及ぼしている活動に敬意を表します。レジ袋の実態を知るために海での体験学習を通しての提案型で進めている取り組みが、地域の農家さんがプラスチックコーティング肥料不使用の米作りにまで影響を及ぼしている活動は、まさにThink Globally,Act Locallyといえます。
特別賞協会会長賞を受賞した「和歌山県田辺市立本宮中学校」では、紀伊半島大水害の復興から、山の道を修復する道普請に始まる観光客へのおもてなしに広がった取り組みに敬意を表したいと思います。私は仲間と「山の道」を保全・修復する活動を進めておりますが、世界遺産学習にとどまらず、熊野古道の損傷が激しい個所を修復する「道普請」の実践に感動しました。「ふるさとへの愛と絆」を深めながら、地域の誇りを刻んでいる姿に日本の未来への希望を持つことができました。
受賞された学校にとどまらず、今回各県から推薦された学校の多くは、学校の校舎や校庭の中だけで学習するのではなく、「地域とのつながり」を持って活動し、いわば地域という「屋根のない学校」の中で学び、工夫し、活躍しているものでした。地域での学習プロセスを通じて、児童・生徒、そして学校が地域の方と協力、協働・コラボレーションをして学び合いの関係性を構築しています。さらに受賞された学校にとどまらず応募された学校の取り組みには、日本全体での課題でもある「地方創生」のヒントが多くあったと思います。まず、気づきがあり、共感し、共鳴し合い、さらに共創していく地域づくりのプロセスを大事にした取り組みこそ、今、一番に求められていることと再確認することができました。
「余白」が感じられない昨今の日本社会において、小・中学生の未来への視野を広げていく活動は一部の大人にみられている権威主義ではなく、地域の足元の課題から一歩一歩進めていく学びと活動は、希望という「静かな情熱」により世代を超えた「協働」と「共創」による地域の変革のうねりとなると期待し、日本の未来への確かな処方箋と確信することができました。